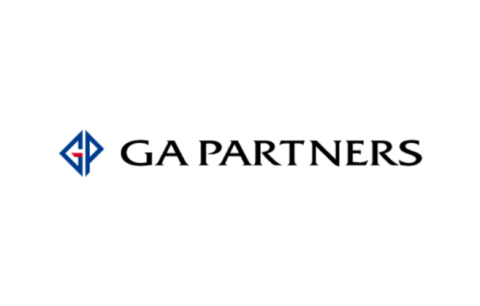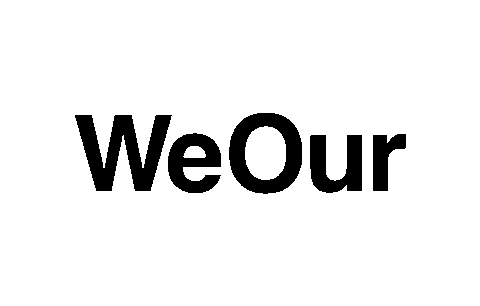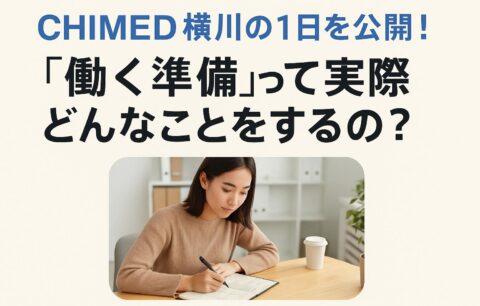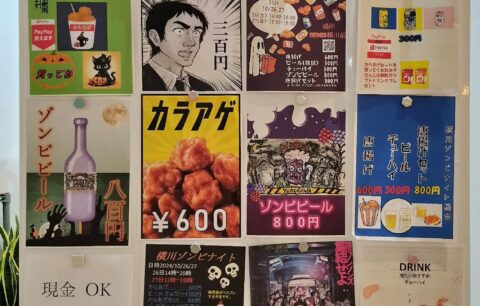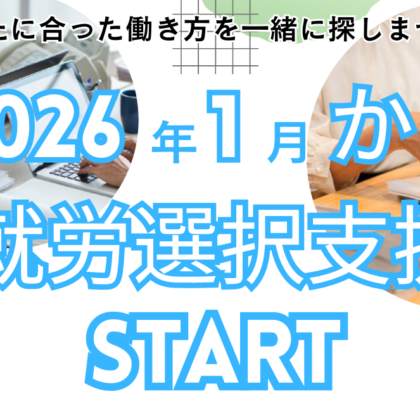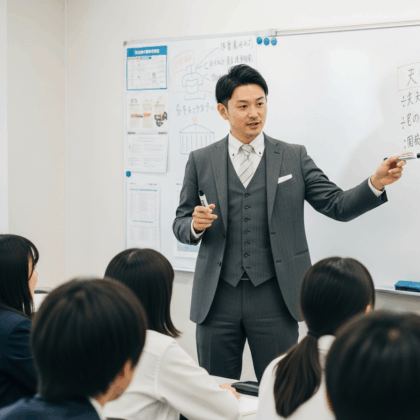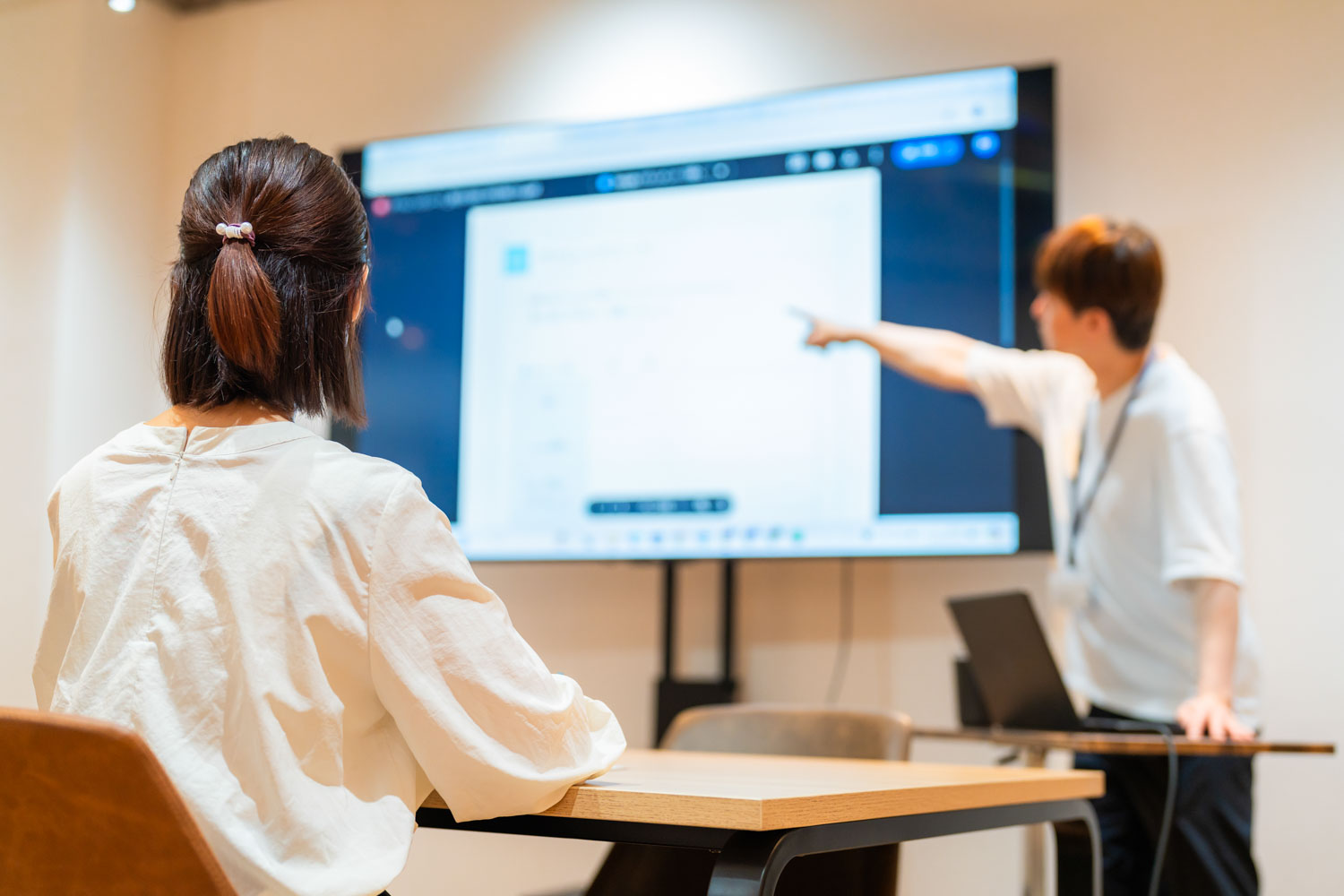障害者雇用促進法のもと、多くの企業が障害者の雇用に取り組んでいます。しかし、現場では「どのような仕事を任せればよいのか」「受け入れ態勢はどう整えるべきか」「社内の理解をどう得るか」といった課題も多く聞かれます。
障害者雇用を成功させるために重要なのは、法定雇用率を「満たす」ことよりも、障害のある方が「安心して長く働ける職場をつくる」ことです。単なる数値の達成にとどまらず、継続的・安定的な雇用につなげるために、企業にとって重要な視点をいくつかご紹介します。
1.業務の切り出しと「できる仕事」の設計
障害のある方に仕事を任せる際、つい「配慮しすぎて任せられない」あるいは「他の社員と同じ業務を求めてしまう」といった両極端になりがちです。実際には、業務内容を細分化・整理し、その人の特性やスキルに合った「できること」から任せる設計が重要です。
たとえば、事務職において「データ入力は得意だが電話応対は難しい」方には、入力作業を中心とした業務設計を行い、コミュニケーションの負荷を調整することで、ストレスなく力を発揮できます。これは「業務の切り出し」と呼ばれる方法で、多くの企業で成果が出ています。
また、「この仕事ができるようになったら、次はこれ」というように、ステップアップを意識した配置もモチベーション向上につながります。
2.受け入れ体制と社内文化の整備
障害者本人が働きやすい環境を整えることはもちろん重要ですが、同時に「受け入れる職場側」の体制づくりも鍵を握ります。
特別な制度や費用をかけなくても、日々のちょっとした配慮
例えば、「声かけの仕方」「急な変更が苦手な方へのスケジュール提示」「静かな作業場所の確保」など が、定着率に大きく影響します。
また、「特別扱いではなく、個別対応」であるという考え方を、職場全体に浸透させることも大切です。そのためには、受け入れ前後に社内研修やオリエンテーションを行い、職場全体の理解を深めることが有効です。
◆ 合理的配慮の具体例
合理的配慮とは、障害のある方が職場で不利にならないようにするための「現実的で過度でない調整」のことを指します。以下は実際によくある配慮の例です
精神障害のある方への配慮:急な指示では混乱を招くため、業務内容を文書やToDoリストで明示し、優先順位をわかりやすく提示する。
知的障害のある方への配慮:業務手順をマニュアル化し、視覚的に理解しやすいようイラスト付きの手順書を用意する。
発達障害のある方への配慮:周囲の雑音が気になる方には、イヤーマフの使用や静かな作業場所を用意する。
身体障害のある方への配慮:車椅子利用者が通行しやすいよう、動線の確保や机・設備の配置を工夫する。
聴覚障害のある方への配慮:口頭での説明に加えて筆談やチャットツールを活用し、情報伝達の漏れを防ぐ。
これらは一例ですが、「その人にとって働きやすい環境とは何か」を対話を通じて確認し、できる範囲で調整していく姿勢が重要です。
3.外部支援機関との継続的な連携
障害者雇用を企業だけで完結させる必要はありません。むしろ、外部支援機関と連携することで、採用から職場定着までを無理なく、そして効果的に進めることができます。
たとえば、就労移行支援事業所では、実際に職場で働くことを見据えた訓練や職場実習を通じて、企業に適した人材を育成しています。採用時にマッチングを相談できるほか、就職後も「定着支援」という形で継続的に支援が受けられます。
また、地域障害者職業センターやハローワークも、障害者雇用のノウハウや助成金情報の提供、職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣など、多岐にわたる支援を行っています。企業がこうした支援機関とつながっておくことで、雇用の安定性が格段に高まります。
まとめ:障害者雇用は「人との出会い」で成長する
障害者雇用は、制度や義務で進めるだけでは限界があります。実際に出会い、ともに働く中でこそ、企業も、社員も、障害のある本人も、それぞれの理解が深まり、成長していきます。
誰かにとって「働ける場」をつくることは、結果として、職場全体の多様性や柔軟性を育むことにもつながります。企業にとって障害者雇用は「社会的責任」ではなく、「組織としての進化のチャンス」でもあるのです。
障害者雇用にお困りの企業様はご相談ください。