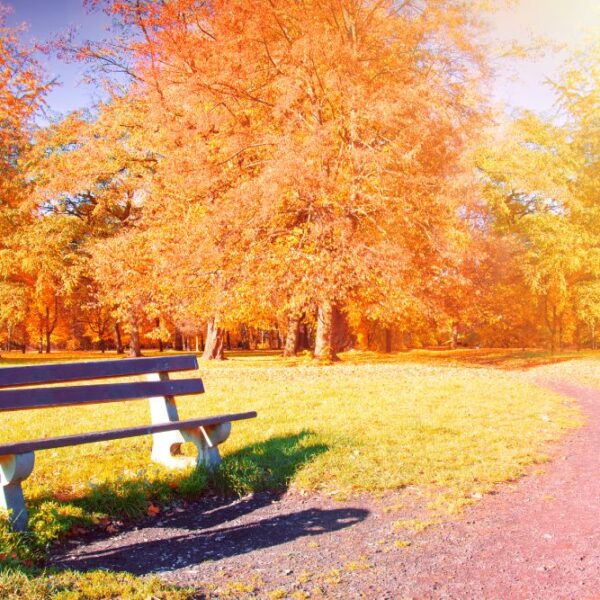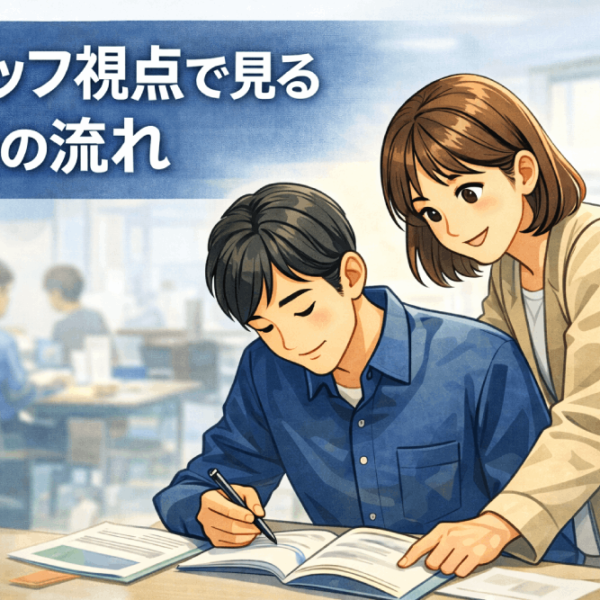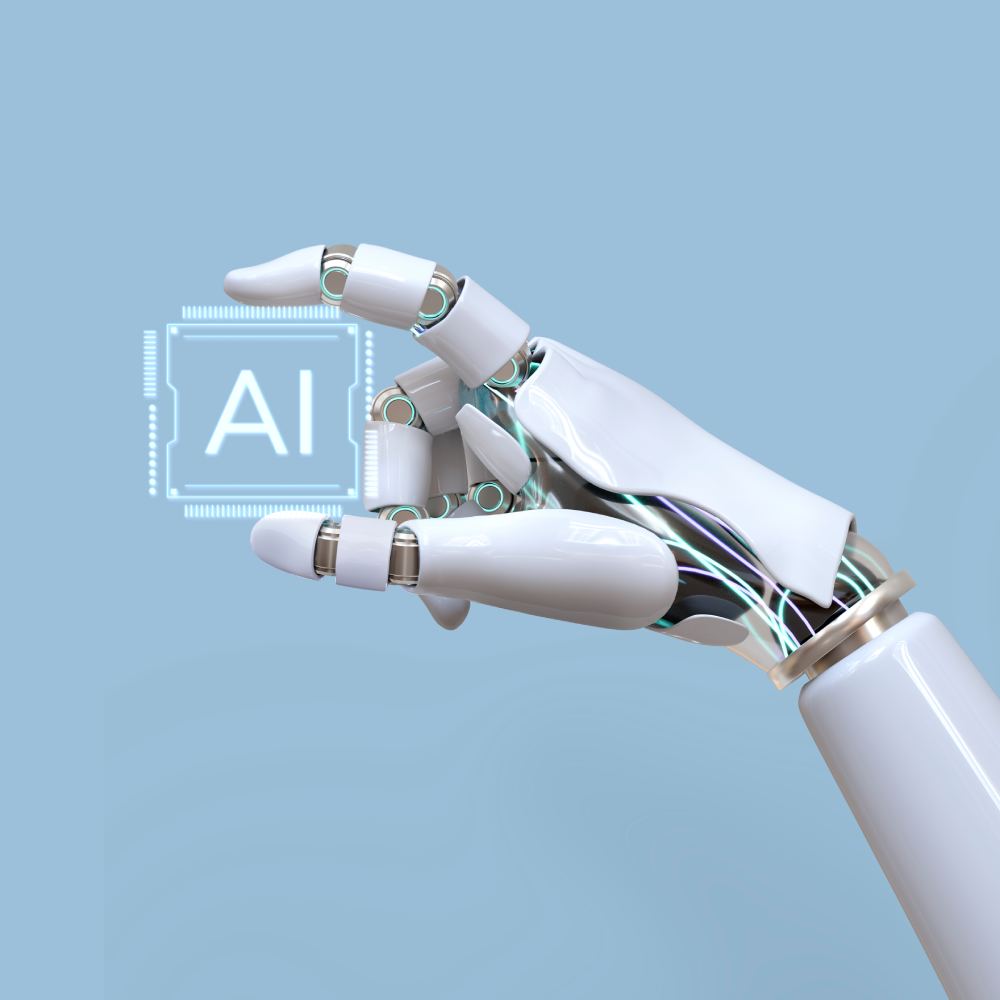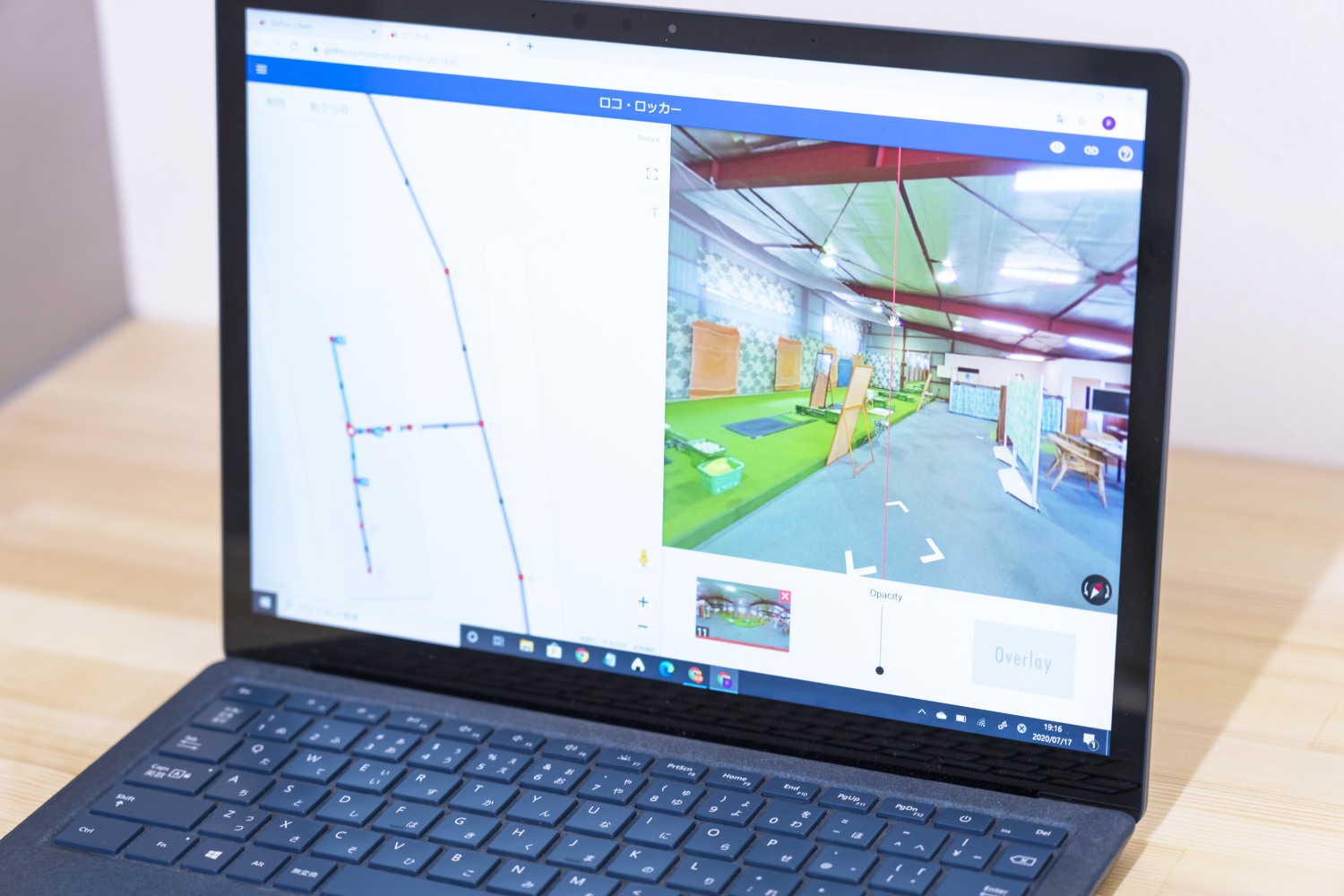毎年夏になるとやってくるお盆。家族や親戚が集まり、ご先祖様を供養する大切な行事です。迎え火や精霊馬など、お盆ならではの風習はよく知られていますが、そもそもお盆がどうやって始まったのかご存知でしょうか?今回は、お盆の意外な歴史とルーツについてご紹介します。
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言います。これは古代インドの言葉「ウッランバナ(ullambana)」を音写したもので、「逆さ吊り」という意味があります。なぜこのような名前がついたのでしょうか?
その起源は、お釈迦様の弟子の一人、目連(もくれん)の物語にあります。目連は神通力を使って亡くなった母親の姿を探したところ、飢えと苦しみにあえぐ「餓鬼道」に堕ちているのを見つけました。
なんとか母親を救いたいと願った目連にお釈迦様は、「夏の修行期間の最後にあたる7月15日に、多くの僧侶に供物を捧げなさい。そうすれば、その功徳によって母親は救われるだろう」と説きました。目連がその通りにすると、母親は無事に救われたと言われています。
この故事にちなんで、毎年7月15日に先祖の供養をする仏教行事が始まり、それが日本に伝わって「お盆」のルーツになったとされています。
仏教が日本に伝来したのは飛鳥時代と言われていますが、お盆が一般に広まったのは江戸時代以降です。仏教の教えだけでなく、元々日本にあった祖霊信仰と結びつき、独自の文化として発展していきました。
祖霊信仰とは、亡くなったご先祖様の魂は子孫を見守ってくれるという、日本古来の考え方です。この信仰と結びついたことで、お盆は単なる仏教行事ではなく、ご先祖様が家に帰ってくる期間として捉えられるようになりました。
迎え火や送り火を焚くのは、ご先祖様の霊が迷わずに家とあの世を行き来できるようにするため。精霊馬のきゅうりとなすは、ご先祖様が少しでも早く帰ってこられるように馬に見立て、ゆっくりと帰っていくために牛に見立てたものと言われています。
お盆の時期が、新暦の8月に行う地域と、旧暦の7月に行う地域に分かれているのはご存知でしょうか?
これは明治時代に新暦が採用された際、農作業などで忙しい時期と重なるのを避けるため、一月遅れの8月に行うようになった地域が多かったためです。東京など一部の地域では新暦の7月15日を中心に行われますが、多くの地域では8月15日を中心に行われています。
お盆は、インドの仏教行事である盂蘭盆会がルーツとなり、日本の祖霊信仰と融合して独自の文化として発展してきたことがわかります。ご先祖様を敬う気持ちは今も昔も変わりません。お盆の歴史を知ることで、また違った気持ちでこの時期を過ごせるのではないでしょうか。